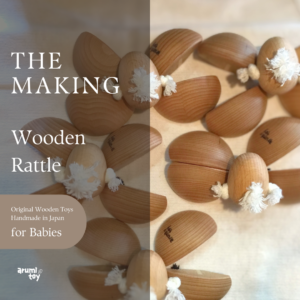創作玩具公募展の審査員をやってきました。裏話。

こんにちは。木工作家のあるみです。
2025年1月末、『小黒三郎賞・創作玩具公募展2025』の審査員審査をやってきました。
大役を仰せつかり、務めを果たしてまいりました〜🙌
岡山県美作市にある現代玩具博物館で長きに渡り行われていて、
私も何度も目にしたことのある公募展です。(出展したことはないのですが・・・)
初めてお問い合わせをいただいた時は、「出展しませんか」とかだと思ったので、
まさかのそっち側!?😱ってなりましたよ。もちろん。
打合せの中で、私が駆け出しの頃から名を知る相沢康夫さんも審査員をされると聞いてだいぶ怖じ気づきました。
ご一緒させていただいた今となっては、とっても気のいいオジサマで仲良くなったのですが、
当初は名前を拝見しただけでビビる存在でしたから。(学生の頃、憧れのNaef社のカタログにYasuo Aizawaっていつも載っていて、どんなにキレッキレの人なんだろう・・って思っていたので)
初対面のご挨拶では、ろくに自分の名前も名乗れないぐらい硬直しました😅
そんな、私の個人的なことはさておき、審査の事をば。
審査員審査は、相沢康夫さん、中山芳一さん、多胡歩未の3人で行いました。
この公募展のおもしろいところは、大人審査(審査員がやる)と子ども審査(4〜15歳の子なら誰でもできる)が同等だということ!
私が出展する方の立場だったら、ぜひとも子ども審査で選ばれたい!です。
何しろ私のモチベーションは20年前から変わらず子ども達に「ドヤッ」って言いたいだけですので。
子ども達に選ばれるなんて光栄じゃないですか!
おもちゃ界の大御所と、子ども教育のプロに挟まれて、私はめっちゃ自分の立ち位置を考えました。
私は今でもずっと自分の事を『作る人』だと思っているので、どう考えても出展する側なんです。子ども達に「おもしろ〜い!」と言わせることに執念を燃やしているような輩なんです。
それで分かりました。私は作る人のままでいいんだと。この20年の作る人としての経験が必要とされているんだと。
【自分のアイデアをカタチにして相手に届ける】
この視点が私の審査基準です。
一生懸命遊ぶしかない
そうなると、もう、一生懸命遊ぶしかありません。
いや、仕事ですけど、遊ぶしかない!




↑必死で遊んでおります。
全ての資料に目を通し、全ての作品で何度も遊びました。
遊ぶだけじゃなくて、作り方とか仕上げとか、コンセプトとか全部見ます。
おかげで時間を超過してしまい、皆さんにご迷惑をかけまくりました。
審査の基準
資料と作品を何回でも見直して、3人で何度も話し合います。
一日目が終わった後も、宿で資料を読み返しました。




作品と資料(エントリーシート)を並べると、作者の意図のようなものが見えてくるのですが、深く考えてじっくり作られた作品、アイデアに絶対の自信を伺わせる作品、作る事が好きすぎる作品などいろいろあります。
その中で、軸が一本通っている作品はやはり訴求力があります。作者の想いと作品のエネルギーが一致している感じです。
どのおもちゃがどんな風にいいのかなどは、図録の講評に詳しく書かせていただきましたので、ご興味のある方は入手していただければと思いますが一部抜粋します。
おもちゃは、『手にした誰かが楽しめるかどうか』が最も大切で難しいところだと思います。作る事にこだわり過ぎると見えてこない部分でもあります。自分の表現したい部分と他者が面白いと思う部分が一致するまで試行錯誤がなされたものは、ストレートに相手の心に届く作品になると思います。
ここには挙げていませんが、作り手の意図とは別のところに面白みのある作品もいくつかありました。ひとまず完成した作品で誰かに遊んでもらうといいです。一度完成したものから削ぎ落として出てきた面白さに辿り着くとそれが作品の強さになりますから。
自分のアイデアをカタチにして相手に届けるというのは、独りよがりでは絶対に成せなくて、意地でできるものでもなくて、自分を受け入れ相手も受け入れられた時に、自ずとすんなり届くものだと、今なら思います。
審査をする中で、駆け出しの頃の自分に出会えた気がしました。上記↑に書いたことは、当時の私に向けての言葉でもあります。
誰かに言われて嬉しかったことや悔しかったこと、自分の行動に対する責任、反省から導き出された哲学とか、
全部吸収して今があって、逆の立場になるとそれらは自分の基準になっているのだと知りました。
貴重な体験をさせていただき、お声がけくださった現代玩具博物館の館長、副館長さんには感謝しかありません。
私自身もこの先の今は見えていない景色を見に、まだまだ進みたいと思います。
審査後
大役果たして肩の荷降りたので、仕事じゃなくて遊んでいます。


ネフの積み木で『だるま』を完成させて喜んでいるところです😅
2025年受賞作品はこちらでご覧いただけます↓。